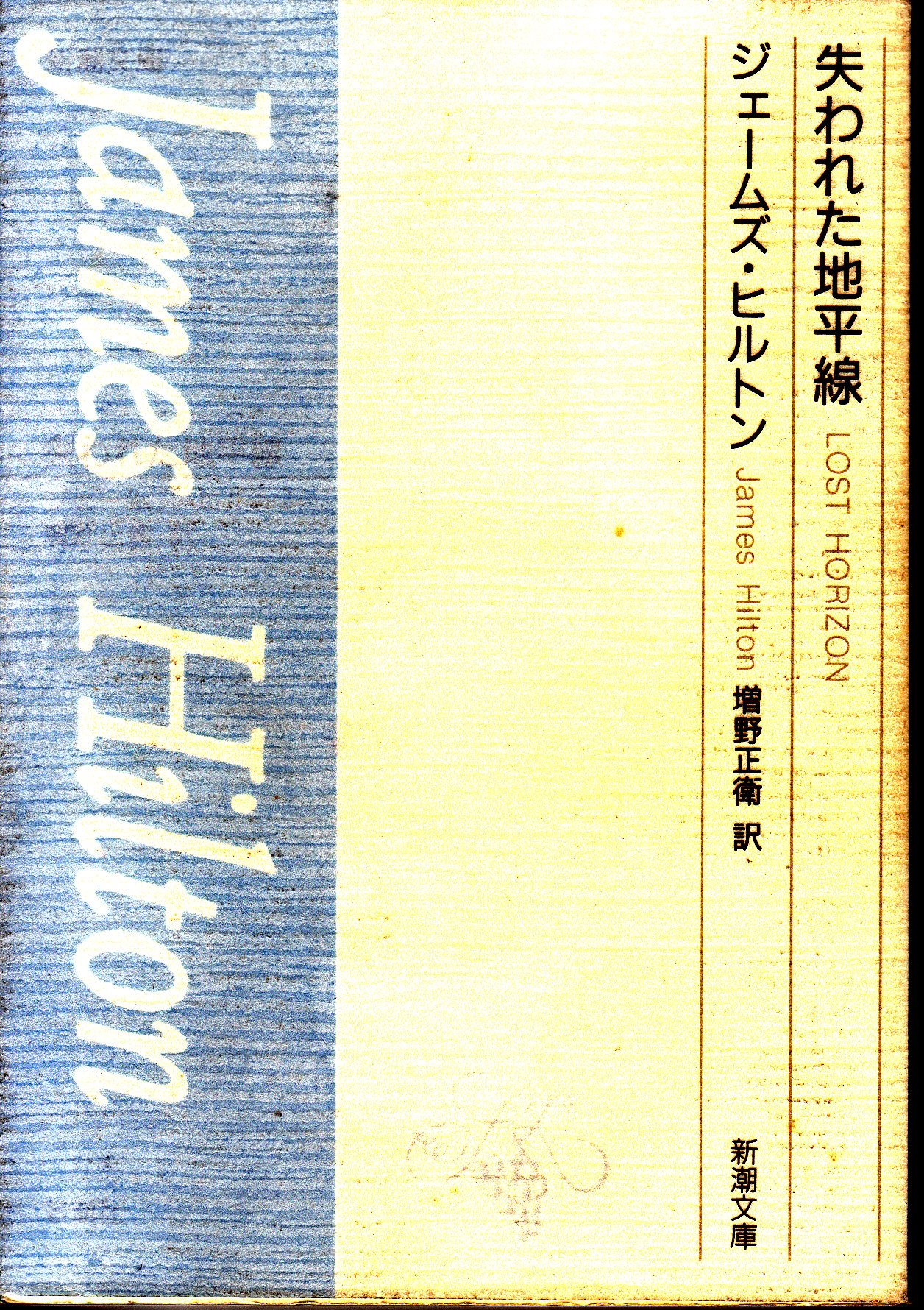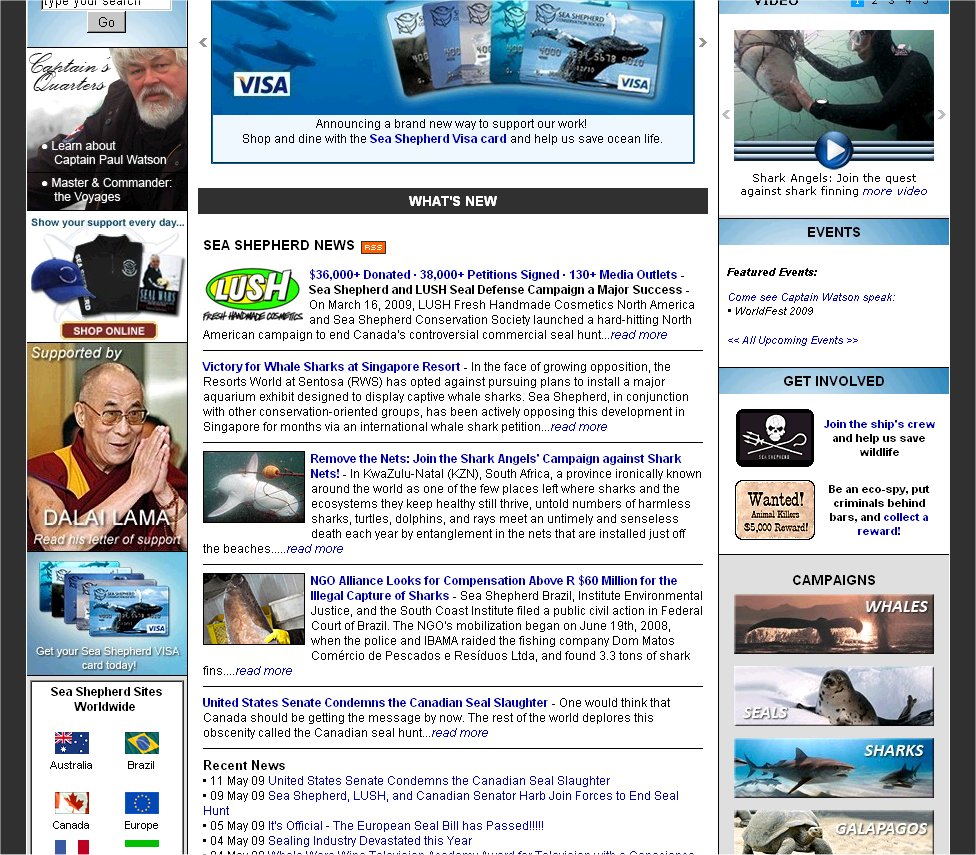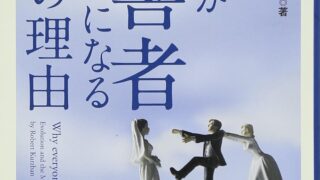 科学技術哲学
科学技術哲学 わいせつとは性が年配の男性にとって適切に管理されていない状態
歴史上「わいせつ」の要件を具体的に示しえたためしがない、というのはよく言われることで、それはそれで正しいと思われる。 だが進化心理学的視点に立てば「わいせつ」を過不足なく単純に定義することは容易だ。性が社会≒権力≒年配の男性(の同盟)にとって適切に管理されていない状態 だ。そもそも具体的にどんな行為や表現であるかは問題ではないのだ。たとえば、一夫一婦制は社会的にひとつの安定解だから、夫婦間の性は基...