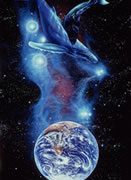ガイア教の天使クジラ
ガイア教の天使クジラ ガイア教の天使クジラ32 人間の思考に対して働く時代精神の制約がいかに強力なものであるか
【第31回】 【目次】 【第33回】 歴史上存在した生物の由来に関する理論は、創造論と進化論のふたつだけというわけではない。 もちろんそれは最も重要な境目には違いないが、『種の起原』が出版されたと同時にスイッチが切り替わるように前者が後者に置き換えられ、以後そのままであるかのような印象を抱いているなら誤りだ。 それはあくまで第28回で少し触れたような、我々が歴史を理解しやすくするために必要な簡便法...